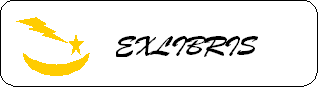美しい文庫本
自分の蔵書の中で‘これは美しい’という文庫本をあげるとすれば、まず辻邦生の『風の琴』(文春文庫)だろう。西洋美術史を代表する二十四枚の名画に、それぞれが喚起するイメージにちなんだ物語を添えた短編小説集だ。
同じ文芸春秋社から出ていた『十二の肖像画による十二の物語』『十二の風景画への十二の旅』の二冊を合本したもの。こちら文庫には小さいなりの凝縮感があって、オリジナルの単行本を凌駕する魅力がある。

スマートな文体を誇る辻邦生。選ばれた絵も、彼の趣味のよさを伝えてくれる。
カバー絵にも使用されたコローの『モルトフォンテーヌの思い出』をはじめ、レンブラントの『黄金の兜の男』、ポライウォーロ『婦人の肖像』(画像)、ブロンツィーノ『ラウラ・バッティフェルリの肖像』、バルトロメオ・ヴェネト『婦人像』、クロード・ロラン『シバの女王の船出』、ジョルジョーネ『嵐』、フリードリッヒ『ドレスデンの大猟場』等々、上品かつ渋好みのオンパレードではないか。
小説も一流の名人芸を堪能できるものばかりだ。いちばん読み返したのは、セザンヌの『サント・ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』に奉げた「地の掟」という作品。人間の男を愛した巨人族の女の悲劇に、涙腺の弱い自分は何度も泣かされた。

------------------------------------------------------------
ページレイアウトの美しさから言えば、『ビリチスの歌』(角川文庫)が筆頭か。
画像(相変わらずヘタだなあ)は昭和四十七年の再版、――三十七年の初版時はどうだったか判らないが――全頁、緑のインクで印刷されている。今でこそ、文庫でもカラーインクの使用はめずらしくない。けれど当時は、かなり画期的で贅沢な試みだったろう。この詩集には、出版側がそこまでこだわった事情が含まれているようだ。
『ビリチスの歌』は、フランスの象徴派詩人ピエール・ルイスが、紀元前ギリシャの女流詩人に成りすまして創作した虚構の古代詩集。オリジナルが出版された当時、「世紀の大発見」とヨーロッパに大センセーションを巻き起こした。「前にビリチスの詩を読んだことがある」とルイス宛に手紙を書いたアテネの大学教授もいたそうだから、その偽装が完璧であったことがよくわかる。
詩は、同性愛と遊女生活が醸し出す濃厚なエロスの匂いを吹きかけてくる。
表現は隠しどころなく、きわめてストレートだ。ひとつ例をあげてみよう。
“ほんの小さな子供だけれど、妾たちは、裸で踊るの。ねえ、どんな踊りか解るわね。アフロディナの 十二の欲望よ。お互い同志、眺め合ひ、裸を較べ、その美しさに感心するの。
見物の方々のお楽しみにと、長い夜通し、妾たちは肉體(からだ)と肉體を温め合った。故とさうする譯ではなくて、すっかり夢中になってしまうの。隣同志で謀らって、扉の後ろに連れこむ女も、時々見かける位だわ。(『女同志』)“
驚くべきは、太平洋戦争末期の最悪の状況下、この詩集の翻訳に着手した窪田啓作・加藤周一の両名の翻訳者魂と、さらに戦後の困窮の真っ只中、二人の訳業を引き継ぎ、十数年におよぶ加筆訂正を経て刊行にこぎつけた鈴木信太郎の執念である。憧れは恐怖を克服する。彼らは『ビリチスの歌』が持つ、艶麗な言葉の香りに魅せられたのか。
時は流れ、氾濫する音と活字の渦に呑まれた人々は、言葉の花の芳香を求め、それに酔い痴れることのできる素直な感受性を忘れてしまった。人畜無害な「何やら詩のようなもの」を舌先で玩んではよろこぶ輩に、訳者たちの真摯な志が伝わる可能性は低い。むしろ彼らは、その率直なエロスを便所の落書きといっしょくたに扱うかもしれない。だから、再版されない方がよい本だと自分は思う。


|